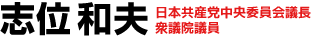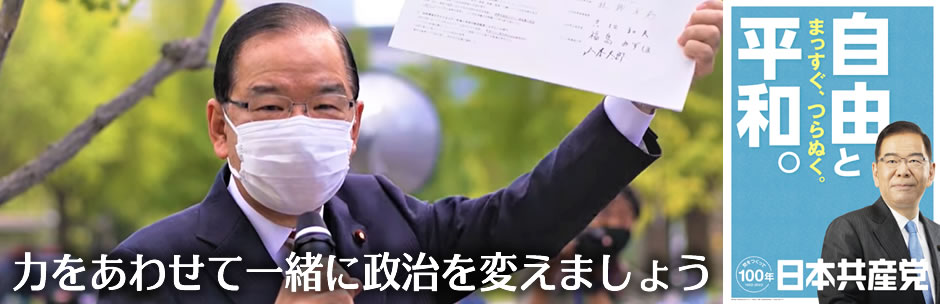2025年11月5日(水)
『資本論』と現代を語る 志位議長と斎藤幸平氏の対談から
第1回 共産主義とはそもそもなにか?
 (写真)対談する斎藤幸平東京大学准教授(左)と志位和夫議長(YouTubeから) |
日本共産党の志位和夫議長と、マルクス研究者の斎藤幸平東京大学准教授がインターネットメディア「ReHacQ」(リハック)で行った対談「マルクス『資本論』の真実」(前半部分は10月24日、後半部分は30日に配信)から要点を連載で紹介します。
対談は配信直後から大反響を呼び、11日間で46万回(11月4日午後7時現在、前後半の合計)視聴されています。「バリバリの資本主義者ですが、このような話は貴重。大変勉強になりました」「愛国心のある右派だが、今回の動画はとても好き」など、多様な視聴者が計3654件のコメントを書き込んでいます。
斎藤氏は「ビッグ企画」の「超スペシャルゲスト」として志位氏を紹介。志位氏の著書『Q&A いま「資本論」がおもしろい』(赤本)と『Q&A 共産主義と自由』(青本)をベースにしながら、「大きな問題が山積みになった日本社会を変えるためにも、もう一つ大きな視点が必要なんじゃないかということで、われわれの専門でもあるマルクスにさかのぼって、2時間たっぷり、お話をうかがいたい」と切り出しました。
ベルリンでの出会いから対談の実現まで
対談のきっかけは、約1年前にベルリンの国際会議に出席した志位氏を、ハンブルクにいた斎藤氏がかけつけて面会したことでした。志位氏は「いろんな話をしましたよね。特にウクライナの問題とともに、ガザのジェノサイドを止めなければならないと。あのときに(斎藤氏から)対談しませんかと言われて、いいですよと(答えた)」。斎藤氏は「私はマルクスをやっているけど、共産党員ではない。こちら(志位氏)はマルクスプラス共産党ということで、(マルクスをめぐり)いろんな流派とか解釈とか運動もある中で、接点がいままでなかった」と振り返りました。
志位氏が「今度初めて対談が実現してよかった」と述べると、斎藤氏は「リハックで(対談を)やりたいなというのが(私の)強い願いで、それを引き受けていただいた。本当に感謝しています」、「資本主義信奉者」も視聴するリハックで対談を行えば、「『意外に志位と斎藤いいことを言っているな』『マルクス面白そうだな』と思ってくれる人が出てくるのではないかと期待して、いろいろ聞いていきたい」と話しました。
「各人の自由な発展が、万人の自由な発展の条件であるような一つの結合社会」
対談の最初のテーマは「共産主義とはそもそもなにか?」。斎藤氏は「『資本主義に問題があるのは確かにそうかもしれんが、そこからなんで一気に共産主義まで行っちゃうの』と思う方が結構多い」「共産主義は全体主義、独裁、不自由な社会みたいなイメージがなんとなくある。共産主義はそもそもなんなんだ?」と問いかけました。
志位氏は、マルクスの盟友エンゲルスが亡くなる前年の1894年に、イタリアの社会主義者ジュゼッペ・カネパから手紙をもらい、未来社会のスローガンを一言で教えてほしいと要請されたことを紹介しました。エンゲルスは返事の中で『共産党宣言』の次の一節を引用しました。(パネルを示す)
「各人の自由な発展が、万人の自由な発展の条件であるような一つの結合社会」
人間は誰でも自分の中に科学、芸術、スポーツ、ものづくり、ケアなどの素晴らしい潜在的可能性を持っていますが、資本主義の世の中では自分の可能性を十分に実現できる人は一握りにとどまり、自分の可能性を生かしきれずに埋もれてしまう場合が少なくありません。マルクス、エンゲルスはすべての人間の「自由な発展」をどうすれば実現できるかというテーマを「若いときから亡くなるまで一貫して追究した」と、志位氏は強調しました。
「自由に処分できる時間こそ、人間と社会にとっての真の富」
斎藤 その(『共産党宣言』が出版された)1848年というのは、マルクスが若かったころ、30歳ぐらいのときの作品で、(その時点ですでに)こういうこと(「各人の自由な発展」)が言われていて、これがずっと後に書いた『資本論』とか、そういう作品の中まで一貫していると。
志位 一貫しているんです。彼(マルクス)は、最初は、分業が悪いと思ったんですね。分業があるから、人間は自由に発展できないと思った。
斎藤 『ドイツ・イデオロギー』(1845~46年)ですね。
志位 そうです。そして分業の廃止を唱えたんだけど、分業というのは、どんな社会になっても、ある範囲では必要です。
ではどこで条件を見いだすかということで、マルクスが1850年代から本格的な経済学の研究を始めて、そこである匿名のパンフレットに出会うのです。大英博物館で。そこには「自由に処分できる時間こそ、人間と社会にとっての真の富だ」という言葉があった。ディルクという人が書いた。それを(マルクスはノートに)書き留めて、自分の経済学の中心に据えていく。
すべての人が十分な「自由な時間」を持てるようになれば、自分の中に眠っている可能性を開花させることができるだろう。資本主義から社会主義に移行して搾取がなくなり、浪費もなくなり、労働時間がうんと短くなって、「自由な時間」がうんと増える。「自由な時間」が増えたら、みんなはそれを自分の発展のために使うだろうと。知的・精神的なさまざまな発展のために。
「赤本」では「自由時間」にかなり注目している
斎藤 資本主義では「自由な時間」を持てない。
志位 奪われている。搾取によって、お金だけでなく、時間も奪われている。
斎藤 なるほど。
志位 先(の社会)に進めば、それ(搾取)がなくなって、「自由な時間」を持つことができる。そして、「各人が自由に発展」していけば、それは「万人の自由な発展」、つまり社会全体の自由な発展につながって、いわば個人の発展と社会の発展との好循環が生まれてくる。そこにマルクスは未来社会の一番の値打ちを見いだしたと私は思います。
斎藤 時間こそが、「自由時間」こそが。
志位 真の富だと。
斎藤 確かに今回、特に「赤い本」を読んだときに、一番大きなテーマになっている話は「自由時間」ですね。これに、いまおっしゃったように(志位氏は)かなり注目している。
志位 そうですね。もちろん人間が生きていくうえで物質的な富は必要です。けれども、物的富さえあれば本当に豊かか。そうは言えない。やっぱり「自由な時間」が必要だと。それがあってこそ、人間が発展できるというのがマルクスの考え方ですね。
斎藤 一般的に、マルクスとか社会主義というのは、労働者の搾取をやめさせようとか、労働組合を使って賃金を上げようとか、資本家をやっつけて平等な社会をつくろう(ということだといわれる)。平等がよくキーワードになると思うんですけど、いまの話だと、むしろ自由。
志位 やっぱり「人間の自由」が最大のキーワードだと思いますね。「人間の自由で全面的な発展」。これが、最大のキーワード。
「生産者が主人公」とはまったく無縁だった旧ソ連社会
旧ソ連では「人間の自由」が発展しなかったという話題に移り、志位氏は「働く人が主人公でもなんでもなかった」という根本問題を指摘しました。
志位 マルクスの未来社会の特徴付けで「結合した生産者の生産様式」という言葉があるじゃないですか。
斎藤 アソシエート。
志位 そう。アソシエートのこと。つまり、自分の自由意志で結合した(アソシエート)生産者が社会の主人公なんだと。これは社会主義、共産主義の根本命題です。
斎藤 つまり、資本家に、企業に雇われてボスの命令で無理やり働くのではなくて…。
志位 そうじゃなくて、自分の自由意志で結びついた生産者、労働者が社会の主人公になって、生産手段もみんなで持って自分たちで民主的に管理、運営していくと。これがめざしていた未来社会だったと思うんです。
(旧)ソ連は全くそれとは異質の社会だった。専制的な官僚によってノルマをおしつけられて、奴隷的な労働を強いられていた。確かにソ連では国営化はやられていた。集団化もやられていた。しかし生産者は主人公じゃなかった。これが一番の問題だろうと思います。そのうえに政治の面では、特にスターリンになって大量弾圧がやられて専制主義の国家がつくられた。だから私たちは、旧ソ連の社会は、経済でも、政治でも、社会主義とは無縁の社会だったと考えています。
人類未踏のことを始めようというプログラム
斎藤氏が「社会主義の社会」といえる社会はあるのかと尋ねたのに対し、志位氏は「これが『できあがった社会主義』だといえる国は、いまの世界にないし、そういうことは過去にもない。ですから全く人類未踏のことを始めようというのが、われわれのプランとなる。全く新しいプログラムです」と答えました。
(つづく)