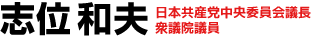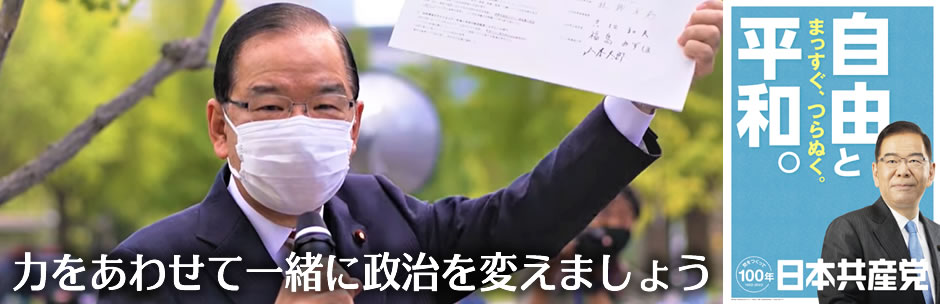2025年10月9日(木)
志位議長の「赤本」講義から(4)
「搾取制度の廃止!」という革命的スローガンを、自分たちの旗に書きしるそう
「赤本」の第5章は、「貧困と格差拡大のメカニズムは?」です。
「赤本」では21世紀の現実を入り口にし、地球規模での貧困と格差拡大を告発した国際NGOオックスファムの報告書を紹介しました。不労所得で富を築く超富裕層は「富を奪う者であり、富をつくりだす者ではない」と、グローバル資本主義の搾取と収奪を印象深く糾弾しています。
社会的規模で拡大する貧困と格差――社会変革のたたかいに立ち上がろう
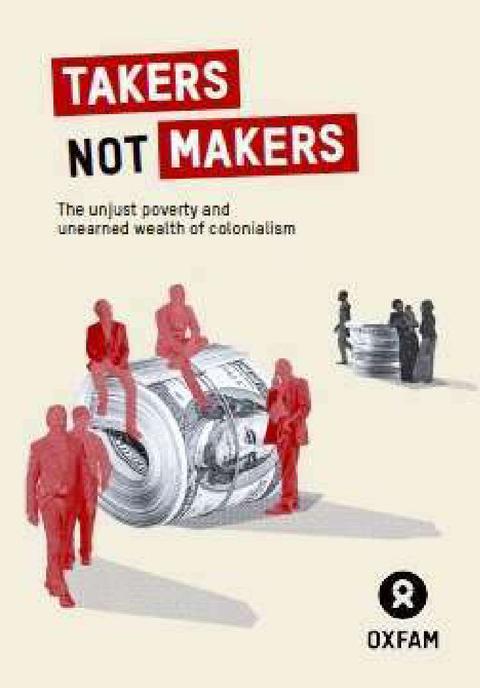 (写真)国際NGOオックスファムの報告書「(富を)つくらず、奪う人々」の表紙 |
『資本論』第7篇「第23章 資本主義的蓄積の一般的法則」では、社会全体で貧困と格差が拡大していくメカニズムが解明されています。その前までは企業内部での搾取関係の解明が中心でした。第23章では大きく視野を広げ、資本の「利潤第一主義」が社会全体をどう変えるか、労働者階級にどのような運命をもたらすかを分析します。まったく新しいステージに分析が進んでいるのです。志位氏は、マルクスの解明の中心点を次のように解説します。
--資本主義には固有の人口法則があります。技術革新の進展とともに、仕事につけない「過剰」な労働者を常に大量につくりだします。マルクスはこれを「相対的過剰人口」「産業予備軍」と名付けました。
--「産業予備軍」の存在は労働者に不利で資本家に有利な情勢を累積的に生みます。労働者全体を資本の支配のもとに縛り付け、社会的な規模で、一方に「富の蓄積」を、他方に「貧困の蓄積」をつくります。
--「産業予備軍」は完全な失業者だけでなく、いつでも解雇できる劣悪で不安定な就業のもとに置かれた雇用者の全体を含みます。現代日本の非正規ワーカーです。非正規ワーカーの拡大と正社員の実質賃金低下は同時進行しており、マルクスが明らかにした法則は日本でも絵に描いたように現れています。
志位 こうした事態を根本的に解決するにはどうしたらいいでしょうか。ここでマルクスが問題にしている貧困と格差の拡大は、個々の企業、個々の産業の問題ではありません。資本が社会的規模でつくりだしている問題です。だから労働者階級がそこから抜け出そうと思ったら、資本主義という社会体制の変革にいや応なしに取り組まざるをえなくなります。社会的規模にまで拡大した資本主義的搾取の鎖を断ち、そのくびきから人間と社会を解放する社会変革のたたかいに立ち上がろうというのが、この章に込めたマルクスの呼びかけでした。
『賃金、価格および利潤』で呼びかけた二つの闘争方向
マルクスは、インターナショナルの会合での演説をまとめた『賃金、価格および利潤』(1865年)で、資本主義的蓄積の一般的傾向が資本家に有利で労働者に不利な情勢を累進的につくりだすことを冷静に明らかにしたうえで、二つの闘争方向を呼びかけました。
--第一は、一般的傾向が不利に働けば働くほど、労働者階級は自らの状態の改善のために、より頑強な日常闘争を行わなければならないということです。マルクスは、もしそういうたたかいを放棄するなら、「救いようのない敗残者の群れに堕してしまうであろう」「もっと大きな運動を起こすための資格をみずから失うことになるであろう」とのべ、労働者に激励のエールを送りました。
--第二は、そうした日常闘争にとどまらず、資本主義的生産を根本から変える社会変革をめざさなければならないということです。マルクスは日常闘争の意義を力説しつつ、それは「一時しのぎの緩和剤を用いているだけであって、病気を治しているのではない」と率直に指摘しました。労働力を売買する資本主義制度そのものを変革する「賃金制度の廃止!」という革命的スローガンを、自分たちの旗に書きしるそうと呼びかけました。
志位 こういう呼びかけは、『資本論』のなかには直接の言葉では書いてありません。インタナショナルの会合での訴えのなかで明瞭な形で書かれています。ここでも『資本論』とインタナショナルでのマルクスの活動を一体的に理解することが重要です。マルクスはこの講演を、資本主義的搾取制度の廃止という「革命的スローガンを自分たちの旗に書きしるそう」という言葉で締めくくっています。これは『資本論』の「第23章 資本主義の一般的傾向」に込めたマルクスの呼びかけそのものであると思います。(つづく)