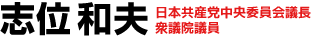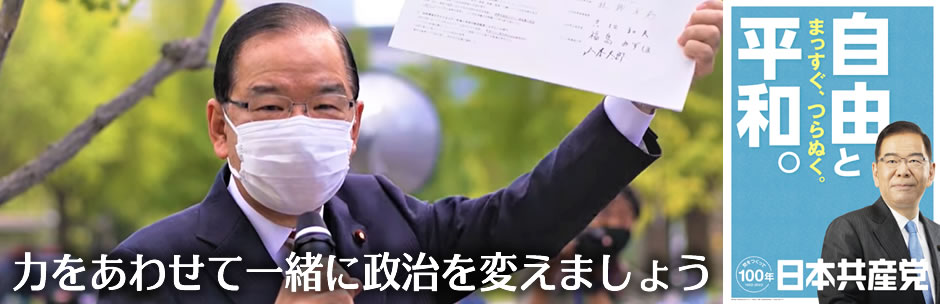2025年9月6日(土)
第6回中央委員会総会
志位議長の中間発言
日本共産党の第6回中央委員会総会の1日目(3日)に志位和夫議長が行った中間発言は次の通りです。
中央役員のみなさんの連日のご奮闘に心からの敬意と感謝を申し上げます。たいへんに重要で積極的な討論が続いていると思います。この中央委員会総会は、文字通り、日本の進路がかかった、そしてわが党の命運がかかった重要な総会となっています。
私は、昨日の幹部会での議論と確認をふまえ、決議案を深める立場で二つの点にしぼって発言します。
“反動ブロック”の危険と対決する“新しい国民的・民主的共同”の提唱について
一つは、決議案が、日本の政治の重大な歴史的岐路にあたって、自民党、公明党、維新の会、国民民主党、参政党などによる“反動ブロック”の危険に正面から対決し、暮らし、平和、民主主義を擁護・発展させる、“新しい国民的・民主的共同”をつくることを呼びかけていることについてです。
参院選後生まれた情勢の危険性とともに新たな可能性と条件を分析して
この提唱は、まず何よりも、参議院選挙後に生まれた情勢――その危険性とともに新しい可能性と条件を分析して打ち出したものです。
選挙後、わが党は、他の野党のみなさん、市民運動のみなさんと、さまざまな形で意見交換をすすめてきました。新しいたたかいに協力してとりくんできました。
私たちは、そういう意見交換やとりくみを通じて、現在の情勢を前向きに打開する“新しい共同”をつくりあげていく条件は大いにあると感じてきました。そして、こうした呼びかけをすることは日本共産党の責任だと考えて、決議案で提起したわけであります。
欧州における極右・排外主義とのたたかい――多くの学ぶべき教訓が
 (写真)発言する志位和夫議長=3日、党本部 |
同時に、私たちがこの方針を打ち出すにあたっては、欧州における極右・排外主義とのたたかいの経験を参考にしました。
昨年、8月から9月に、わが党代表団が、欧州3カ国(ドイツ、ベルギー、フランス)を歴訪しましたが、このときの一連の会談では、排外主義とのたたかいが意見交換の重要なテーマの一つとなり、軍事同盟強化と大軍拡に反対するとともに、排外主義と人権侵害を許さない――この二つを共通の課題として、国際連帯を発展させることで一致しました。
その会談のいわば続きとして、今年8月上旬に、原水爆禁止世界大会の参加のために来日した、イギリス労働党前党首・英下院議員のジェレミー・コービン氏、ベルギー労働党欧州議会議員のマルク・ボテンガ氏、ドイツ左翼党(リンケ)前共同議長・欧州議会議員のマルティン・シルデワン氏と、東京と広島で、それぞれ時間をとって会談をする機会がありました。7月の参議院選挙で日本で起こった情勢の変化、わが党のたたかいについて先方に伝えるとともに、欧州における極右・排外主義とのたたかいについて詳しくお聞きしました。
欧州の左翼・進歩諸党の同志たちは、長期にわたってたいへんな苦労をしながら、この反動的逆流とのたたかいを続けています。私が、一連の会談のなかで感動を持って聞いたのは、ジグザグを経ながらも、また時には重大な後退を強いられながらも、この逆流と正面からたたかうことで、重要な前進をつくりだしているということです。そこには日本のたたかいを前進させるうえで、私たちが学ぶべき多くの教訓があり、ご報告をしておきたいと思います。
イギリス――曲折をへて新しい左派新党結成をめざすうねりが
まず8月2日、東京で、英労働党前党首のコービン氏と会談を行いました。昨年夏、ベルリンでお会いしていらいの再会となりました。
2008年に「リーマン・ショック」がおこり、新自由主義が破綻し、国民との矛盾が激化し、若者たちが大量に労働党に入党するなかで、それにおされる形で、コービン氏は労働党党首に選ばれ、2015年から20年まで党首をつとめました。この時期に、コービン党首は、貧富の格差の是正と社会正義、核軍縮を訴え、労働党は党員を20万人から60万人に増やし、欧州最大の政党になったとのことでした。ただ、コービン氏は、激しい攻撃を受けました。大手メディアは、彼を「国家の安全保障の脅威」といって攻撃しました。米国のトランプ大統領、イスラエルのネタニヤフ首相は、「コービンだけは、首相にするな」と名指しで攻撃をしたとのことでした。そして、労働党は、パレスチナ人の権利を完全に支持し、ガザでのジェノサイドに反対しているコービン氏を、党の公認候補にしないという対応をしたのです。
そういうもとで、2024年7月に総選挙が行われました。この総選挙では、極右政党・リフォームUKが伸長し、得票率14%を獲得しました。保守党は極右に支持基盤を奪われる形で得票率を23%に後退させ、大敗しました。労働党は得票率は33%と振るわなかったのですが、小選挙区制のもとで議席を大幅に増やし、スターマー政権が発足しました。この時、コービン氏は無所属で立候補し、ガザでのジェノサイド反対を訴えぬいて選挙区で圧勝し、5人で無所属の会派をつくったとのことでした。その後、スターマー労働党政権は、国民に犠牲を強いる緊縮政策をつづけ、パレスチナ対応ではイスラエル擁護の姿勢をとり、大軍拡に突き進むなど、国民の期待を裏切るなかで、いよいよ支持を失っています。一方、極右・リフォームUKは支持率で1位になるなど伸長している状況です。
そうしたもとで、コービン氏は5人の無所属議員を中心に左派新党をつくるプロジェクトにとりくんでいるとのことでした。11月に結成党大会を開催するとのことです。党ができる前から、世論調査で支持率が10%を超えるという予想がされています。新党の結成よびかけ文には、「富と権力の大規模な再分配」を行うこと、「ジェノサイドに抗議し、自由で独立したパレスチナを実現」することなどが掲げられています。排外主義に対して、断固反対の立場を次のように明記しています。
「分断をあおる者たちは、私たちの社会の問題は、移民や難民によって引き起こされていると考えさせようとしています。しかし、そうではありません。問題は、企業や億万長者の利益を守る経済システムによって引き起こされているのです」
新党のよびかけには、すでに80万人を超える人々が賛同の署名を寄せているとのことです。
このように、イギリスの同志のたたかいは、大きなジグザグを経たものですが、一貫して社会変革の旗、排外主義に反対する旗を掲げることで、新しい前途を開こうとしている。こういうたたかいがイギリスでも起こっており、今回の会談で、日本共産党は、コービン氏の新党と友好と連帯の関係をつくることで合意したことを報告しておきたいと思います。
ベルギー労働党――極右の発祥地で、一軒一軒訪問し、躍進をかちとった
つづいて、8月4日、広島で、ベルギー労働党・欧州議会議員のボテンガ氏と会談をしました。彼とは、昨年訪欧した際に、ベルリンとブリュッセルでお会いしていますが、突っ込んだ会談は、今回が初めてです。
ベルギー労働党は躍進を続け、直近の2024年6月の総選挙では、得票率9・9%、15議席まで躍進をしています。一方、極右政党・「フランダースの利益」も得票率13・8%を獲得し伸長しました。ただ、この極右政党との長期にわたる正面からのねばりづよいたたかいは、ベルギー労働党の躍進の一つの重要な要因になっていると思います。他にもいろいろな重要な教訓があると思いますが、排外主義と断固としてたたかう姿勢が、躍進の一つの重要な要因となっています。
私が極右とどうやってたたかっているのですかと聞きますと、ボテンガ氏は次のように言いました。
「極右とたたかううえで魔法の処方箋、魔法のレシピはありません。欧州全体で台頭しているし、ベルギーでも北部で強い。極右台頭の背景には人々の怒り、生活の苦しみ、物価が高いが給料が上がらないということがあり、それらの非難をイスラムや移民に向けています。治安やテロ問題もすべて彼らのせいにしています」
私は、「この逆流をうちやぶるカギは『要求を共有する』ことと、『希望を語る』ことにあると考えているのですが」と話しました。そうしましたらボテンガ氏から同じ方向の努力をしていることが語られました。
「私たちの課題は二重です。一つは、有権者の怒りを正当だと認めることです。正当な理由があって怒っているわけで、それを認めることから出発しています。二つ目は、希望を語ることです。物事は変わる、社会は変えられることを訴えています。長期的に社会を変えるプロジェクトとともに、ただちにやるべきプロジェクト、その両方を語っています。極右は現状に不満を持っていることの反映であり、共通の希望を語ることによって、打ち勝てると思います」
さらにボテンガ氏は、ベルギー労働党のメルテンス書記長の地元・アントワープ市での攻防をくわしく語りました。ここではかつて極右が40%の票を獲得していたといいます。アントワープ市というのは、ベルギーとくにフランダース地域の重要都市で、労働者の街であり、港湾があり、産業があり、港湾労働者がいる。ここがベルギーの極右の発祥の地となったとのことでした。彼の話では、10~15年前にはアントワープ市には共産主義者はいなかったとのことでした。
そういうなかでベルギー労働党の同志たちは、10年、20年とついやして、労働者階級のコミュニティーでキャンペーンを展開し、一軒一軒を訪ね歩き、要求を聞き、希望を語り、労働者を一人一人獲得していきました。「公営住宅に入れないのは、スーダン人のお隣さんがいるからではなく、公営住宅が足らないことが問題なんですよ」と。こういう対話を一軒一軒おこない、獲得していった。いまではベルギー労働党の支持をアントワープ市では20%まで広げたとのことでした。ベルギー労働党のたたかいは、ヨーロッパにおける極右とのたたかいの最大の成功例の一つと、みなされていると聞きました。
ドイツ左翼党――権力と極右の結託に断固反対、選挙での躍進、8万人の新入党員が
つづいて、8月5日、ドイツ左翼党(リンケ)前共同議長・欧州議会議員のシルデワン氏と会談しました。
実は、シルデワン氏とは、1年前に、ベルリンで会談したのですが、その時は、左翼党が非常に苦しい状況のもとでの会談だったのです。極右勢力の台頭にくわえて、有力議員が離党して新たなグループをつくり、一時は、このグループが支持率で左翼党を上回るなど厳しい状況にありました。会談の前日に、左翼党が強固な支持を持っていたテューリンゲン州の州議会選挙で、極右政党・AfD(アーエフデー)――「ドイツのための選択肢」が第1党になり、左翼党は重大な後退を強いられました。その次の日の会談だったのです。
しかし、シルデワン共同議長(当時)は、丁重かつ温かい心遣いで応対してくれ、たいへんに充実した会談になったのを思い出します。この1年前の会談では、難しい状況のなかでも、左翼党が、この数カ月で8000人の新規入党者を迎えており、そのほとんどが青年と女性だということが話題になりました。あの時に、私が、「これはすごいことではないですか。若い党員は左翼党のどこに魅力を感じて入っているのですか」と聞くと、シルデワン共同議長から、「一つは、欧州における新しいファシズムとたたかっているということです。もう一つは、排外主義に反対して連帯を掲げて一貫してたたかっていることです」との答えが返ってきたことを思い出すと話し、1年ぶりに彼に会って「その後、どうなっていますか」と聞きますと、文字通りの大激変が起こっていることを語ってくれました。
「しんぶん赤旗」でも詳しく報道しましたが、今年2月の総選挙で、左翼党は躍進し、得票率8・8%を獲得し、64議席を獲得しました。ただ、極右政党・AfDも、得票率20・8%、152議席へと伸長しました。そういう厳しいせめぎあいのたたかいをやっているのですが、驚くのは、総選挙での躍進をはさんで、昨年からこれまでに、何と8万人ぐらいのすごい数の新入党者を迎えたというのです。びっくりしました。そのほとんどが若い人だといいます。どうして増えたのかと聞きますと、シルデワン氏は、「それは明確さ、コミュニケーションをとること、そして極右に対する明確な態度です」と答えました。古い保守政治に対するたたかいにとりくみながら、極右に対する明確な態度をとったことが大量入党につながったという説明でした。
この点で、ドイツ政治の大きな転機になったのは、保守のキリスト教民主同盟(CDU)と極右・AfDが結託するという事態が起こったことでした。今年1月、CDUのメルツ党首が主導して、難民受け入れ制限法案が、極右・AfDの支持をえて採択されました。保守政党と極右が結託したのです。これは社会の「ダムの決壊」と言われたそうです。ファシズムと排外主義を許してはならないというのは、ドイツではかなり広いコンセンサスがあります。にもかかわらず保守政党が排外主義と結託した。「ダムの決壊」が起こった。この「ダムの決壊」にさいして、ハイディ・ライヒネック・左翼党連邦議会共同代表が、メルツ氏を厳しく非難して、「私たちが民主主義を守る防火壁だ」と連邦議会で訴えた。この演説動画は2900万回再生され、情勢が一変していきました。これが一つの大きな転機になって、躍進につながっていった。こういう話がされました。
危機はチャンスにもし得る――日本でヨーロッパに負けないたたかいを
イギリス、ベルギー、ドイツの左翼・進歩勢力のたたかいに共通する教訓は何でしょうか。極右の伸長は、たしかに社会にとっての深刻な危機です。左翼・進歩勢力が、それに押される局面もあります。後退を強いられることもある。ジグザグも起こってくる。しかし断固として、正確なたたかいを貫けば――つまり、古い保守政治への正面からの批判と民主的対案・希望を語りながら、極右・排外主義との断固たるたたかいを貫けば、危機はチャンスにもし得る。このことを教えているのではないでしょうか。こうした欧州における階級闘争の弁証法を、つかむことが大切ではないでしょうか。
日本でも、決議案が述べているように、日本共産党が、自民党政治の「二つのゆがみ」を正す改革にとりくむ。同時に極右・排外主義ともたたかう。この「二重の役割」を果たしながら、さらに“反動ブロック”の危険に対決する“新しい国民的・民主的共同”を追求する。この仕事を本当にやり抜けば、日本の情勢は前向きに変えられるし、日本共産党の新しい前進をつくり得る。これをヨーロッパの教訓として、しっかり私たちも学んで、ヨーロッパの同志たちに負けないがんばりをしようではないかということを訴えたいと思います。
「質量ともに強大な党をつくる集中期間」をいかにして成功させるか
「大切なことはわかるが、やり切る自信がない」――この声にどうこたえるか
いま一つは、「質量ともに強大な党をつくる集中期間」についてです。
「集中期間」を成功させることができるのか。目標達成をすることは果たしてできるのか。今日の討論でも、「大切なことはわかるが、やり切る自信がない」という声が、少なからずあるという発言がされました。私は、これは当然、出てきてしかるべき意見だと思います。この声にどうこたえるか。党大会決定にもとづいて、全党のみなさんは、この1年半、強く大きな党をつくるための努力を重ねてきました。にもかかわらず、後退から前進に転ずることができていない。これは事実です。
それでは、「集中期間」を成功させるためのカギはいったいどこにあるのか。昨日の幹部会で、つっこんで議論しました。総会での討論でも、ここに焦点を当てた重要な発言が続いていると思います。私は、それらをふまえて、「集中期間」をいかにして成功させるか、そのカギがどこにあるかについて、三つの角度から話したいと思います。討論の参考にしていただき、率直な議論で深めていただければと思います。
情勢の変化――危機とチャンスは表裏一体の関係にある
第一の角度は、情勢の変化です。
討論のなかで、東京の田辺都委員長は、「後退から前進への反転がどうしたら可能なのかを自問してきた。参院選のたたかい、その後の情勢の変化を踏まえ、私は『できる』と思った」と発言しました。そして「最大の根拠は、日本共産党の役割への期待と注目の新たな広がりだ」とのべました。東京で参議院選挙のボランティアとしてともにたたかった方々は、3年前の参議院選挙を大きく上回って1000人を超えた。自民党政治の「二つのゆがみ」を正す党の姿勢、排外主義に反対する党の姿勢に共感して、入党者が次々と生まれている。街頭でシールアンケート対話にとりくむと、「入党したい」といってきた人、要求対話で結びつき入党に至った人が何人もいる。「東京には膨大な若い世代が存在しているので、伸びしろは無限大だと思う」と発言しました。
愛知の石山県委員長からは、「選挙中の街頭演説に自らの意思で参加してきた青年に声をかけて、結びつきを深め、党に迎える経験が生まれた」こと、「まだまだ少ないけれども、自ら接近してきた20代、30代を党に迎える経験が広がった」ことが報告されました。
これらはまだごく部分的で、萌芽の形での変化だと思いますが、やはり情勢の変化がつくっている動きだと思います。
決議案では、その冒頭で、現在の日本の情勢を分析して、重大な歴史的岐路にあるとズバリ明記しています。一方で、きわめて重大な“反動ブロック”の危険が生まれている。他方で、党の役割が光っている。そして“新しい国民的・民主的共同”をつくる条件が生まれている。“反動ブロック”の危険のもとで、私たちが受動的な対応に陥ったら致命的後退につながっていきます。しかし、本当に攻勢的に対応するならば、わが党にとってチャンスにもなり得る。いまの情勢は、たしかに危険が一方にありますが、それは日本の政治を変えていくチャンスにもなり得る。そして党の新たな前進をつくり出すチャンスにもなり得る。つまり、危機とチャンスは表裏一体の関係にあるのです。
さきほど紹介したドイツの左翼党の経験は、その一つの典型例だと思います。左翼党は一時は極右の攻勢に追いつめられて、ドイツの場合は、比例得票率5%の「足切り条項」というのがありまして、比例得票率がこれを切りますと小選挙区で3議席以上獲得しなければ議席がゼロになってしまうという制度になっています。一時は、5%が難しいとも言われました。しかし、「ダムの決壊」という情勢の転換点をとらえて、攻勢的に対応して、入党者が爆発的に増え、躍進をかちとり、党員を8万人も増やしたわけです。これも、危機は同時にチャンスだということを教えているのではないでしょうか。
参議院選挙は新しい情勢をつくり出しました。私たちは自民党をたしかに追いつめました。これ自身は大きな前進です。しかし、重大な危険も生まれました。その重大な危険のなかで、日本共産党がその値打ちを輝かせて奮闘すべき新しい情勢に私たちは入ってきた。決議案は、この情勢の新しい特徴をとらえて“新しい国民的・民主的共同”をつくろう、という大方向を提起しました。これにとりくむことと一体に、「集中期間」にとりくむならば、目標をやりきる可能性と展望が開かれてくるのではないでしょうか。ぜひ、いま生まれている情勢の特徴を攻勢的につかんで、「集中期間」の成功に生かそうではないかということを訴えたいと思います。
双方向・循環型の活動をつらぬく――決議案の「構成」と「語り方」について
第二の角度は、双方向・循環型の活動をつらぬくということです。
決議案は、ここで提起している「集中期間」の方針の全体が、双方向・循環型でこれを成功させようという姿勢に貫かれたものになるように、常任幹部会、幹部会として、力をつくし、心をこめて仕上げました。
私たちは、都道府県委員長・地区委員長のみなさんから寄せられた参議院選挙を踏まえてのアンケートを何度も読み、詳細な抜粋もつくって検討しました。そこには高齢化をはじめ、党組織が直面している深刻な困難が率直に報告されており、胸がつぶれるような思いで読んだ報告も少なくありませんでした。こうした現実から出発して、どうやって党建設を成功させるか。私たちも悩みながら方針をつくっていきましたが、決議案では次のような決意を書き込んでいます。
「困難を直視しつつ、生まれつつある発展の芽に確信をもち、それをどうやって広げ、大きな流れにしていくか。目標をいかにしてやりぬくか。双方向・循環型のとりくみを貫き、実践をつうじて、みんなでその回答を見つけ出していきたい」
ここが、常任幹部会、幹部会の議論を踏まえて、私たちが「集中期間」をどういう姿勢で成功させるかについての思いを、結論的に込めた部分であります。
今度の決議案の「集中期間」についての方針の「構成」と「語り方」に注目していただきたいと思います。今回の決議案では、党建設について、「ねばならない」という形で方針をならべることは極力さけて、「現に生まれている発展の芽」に光をあてて、これを伸ばし、広げていこうという姿勢を貫く「構成」と「語り方」にしました。
たとえば、「世代的継承を中軸とした党員拡大」の部分です。その「構成」と「語り方」に注目して読んでいただきたいと思います。まず決議案は、「対象者がいない」、「若い世代につながりがない」という、多くのみなさんが共通していだいているであろう悩みから出発して叙述しています。そして、「全国で生まれている次のような発展の芽を伸ばしていこう」として、四つの項目で「発展の芽」を述べています。一つ目は、「要求対話・アンケート」のとりくみが、新しい結びつきを広げ、入党や購読につながる経験が生まれていること。二つ目は、若い世代を対象にした「ミーティング」や「集い」の開催をきっかけにして「つながり名簿」づくりにとりくみ、世代的継承への系統的な働きかけが始まっていること。三つ目は、職場・労働者の分野ごとの「集い」が、職場でのたたかいと労働者の中での党づくりに新たな息吹をもたらしていること。四つ目は、学生支部で、学費値上げ反対など要求運動、「学生オンラインゼミ」がとりくまれ、新しい条件が生まれていること。この四つの項目で、みんなの力でつくってきた「発展の芽」を伸ばそうと訴えています。そして、四つの項目のすべての活動において、「党機関と党支部が協力・共同してとりくみを推進し、『支部が主役』の活動に発展させよう」と呼びかけて結んでいます。こういう「構成」と「語り方」になっているのです。
さらに決議案では、民青同盟への援助の問題を重視して書いていますが、これも民青でいま学習、要求運動、拡大での奮闘が始まっている、これを伸ばしていこうという立場で書かれています。「しんぶん赤旗」読者拡大の問題では、日曜版電子版の発行と電子版読者システム導入という全く新しい画期的条件を生かして、そして「しんぶん赤旗」への社会的注目と信頼の広がりを生かして、思い切った前進をはかろうと訴えています。学習を中心とする党の質的強化でも、参院選の結果をうけて、「もっと党を語る力をつけたい」などと、かつてなく「学びたい」という思いが高まっていることから出発して、この思いにこたえてとりくもうではないかと訴えています。
決議案では、「世代間の協力」について、一項たてて訴えました。高齢化という問題について、この問題にどう向き合うかはずいぶん議論しましたが、1960年代から70年代に入党して、多くの試練にたえて、党の発展を支えてきた同志のみなさんに、自らの党員人生をかけて、力をあわせて世代的継承という大事業をやりとげようということを、心をこめて呼びかけています。同時に、82歳の党員から寄せられた手紙を紹介して、「ベテラン党員、高齢党員、若い世代、真ん中世代の党員の一人ひとりをすべて宝のように大切にして、みんなで力をあわせよう」という呼びかけを行っています。
決議案では、最後に、党機関の問題をのべていますが、これも、全国のすぐれた経験に学んでみますと、結局、党大会決定が明らかにした党機関活動を改善・強化する「三つのスローガン」の実践ということになってくる。とくに、「学習と政治討議を最優先課題として大切にし、目標や方針について納得のゆくところまで時間をとって丁寧に議論」することを重視しようと訴えています。
「率直な議論をして、心通わせる討論ができたことが、そのあとの力になった」
この点にかかわって、討論のなかでの、北海道の千葉道委員長の発言を、とても感動的に受け止めました。千葉さんは、方針をやり抜くには、「決議案が提起した双方向・循環型の活動で、全党の知恵と力を集める、この方針しかない」とのべました。地区委員長会議で、「こういうときこそ機関はあわてないで、落ち着いて支部と党員の率直な思いをよく聞く。お互いに納得するまでとことん議論しよう、疑問が出された場合はそのままにしないで必ず返していこう」と呼びかけた。
そして、幹部会決定を徹底するために室蘭の地区活動者会議に参加した経験を語りました。司会者から「率直な意見を出してほしい」と呼びかけると、10人くらいの方が次々に手をあげて、支部の困難、実情を語り、「道委員会や中央委員会は、支部の実情をつかんだうえで方針を提起しているのか」など率直で厳しい意見が出された。千葉さんや地区委員長が、一生懸命討論で返した。でも「自分自身話しても説得力ないなと思う場面がしばしばだった」「この会議はうまくいかなかったと思って札幌に帰った」とのことでした。ところがこの地区委員会では、翌々日から拡大で大奮闘が始まって、8月、日刊紙でも、日曜版でも、読者拡大で前進をかちとった、本当にうれしかったという報告でした。千葉さんは、発言をこう結びました。
「率直な議論をして、心通わせる討論ができたことが、そのあとの力になったのではないか。支部と党員は困難はあるが、何とかしたいという思いはみんな持っている。この本音の声をいかにして党内で交流して、循環させて、これをエネルギーに転化することができるか。目標達成のカギはまさにここにあると思います」
私も本当にそうだと発言を聞きました。双方向・循環型で学びあって、心を通わせあって、答えを見つけていく。決議案の中のさきほど読み上げた箇所で、「双方向・循環型のとりくみを貫き、実践をつうじて、みんなでその回答を見つけ出していきたい」とのべていることにぜひ注目していただきたい。この箇所は、幹部会での討論を経て修正・補強した箇所です。「みんなでその回答を見つけ出していきたい」ということは、私たちは、まだ全面的な回答を持ち合わせているわけではない、みんなで回答をつくっていこうということなのです。率直な議論で心を通わせ、双方向・循環型で知恵と力を集めて、探求、改革、実践を進めていこう。そのためには党機関の活動のあり方の大胆な改革も必要になるでしょう。ここに、「集中期間」を成功させる二つ目のカギがあるのではないかと思います。
科学的社会主義の学習を正面から位置づける重要性――党大会決定の実践として
第三の角度は、「集中期間」の三つの目標を一体的・相乗的にとりくむことの重要性です。すなわち党員の拡大、「しんぶん赤旗」読者の拡大、そして学習――この三つの目標を一体にとりくむことで新しい可能性が開けてくる、これを新しい前進の条件にしていきたいと思います。
福岡の内田県委員長は、目標をいかにしてやり抜くかの回答の一つとして、決議案が、党大会決定の具体化・実践としてとりくんだ2回の「学生オンラインゼミ」と、それをまとめた二つの『Q&A』――『いま「資本論」がおもしろい』(赤本)、『共産主義と自由』(青本)の学習を提案していることについて、「党の活力をつくりだす提案」ととらえたと語るとともに、この間、県委員会でよく議論をして「赤本」の学習会にとりくみ、それが党に大きな活力を生み出しつつあることを語りました。
科学的社会主義の学習を、正面から位置づけた集中的運動というのは、調べてみましても、党の歴史のなかでも初めてのことなのです。日本共産党は、科学的社会主義を理論的基礎としている党です。そして、科学的社会主義の一番の土台となっているのは何かと言えば、マルクスの『資本論』です。この内容を学び、広げることを、正面から位置づけた運動の提案は今回が初めてのことです。
私が強調したいのは、これが第29回党大会決定にもとづく提案だということです。党大会決定では、党が、1980年代以降、長期にわたる党勢の後退から前進に転ずることに成功していない要因を突っ込んで解明しました。その主体的要因として、およそ10年にわたって新入党員の「空白の期間」ともいうべき時期があり、それが党建設上の方針の誤りと結びついたものであることを明らかにしました。
同時に、「客観的要因の最大のものとしては、社会主義・共産主義の問題がある」という分析を行いました。すなわち、ソ連・東欧の旧体制の崩壊を境に、社会主義というのは「失敗が証明された体制」という見方が広く喧伝(けんでん)され、それに対してわが党は、崩壊したのは社会主義と無縁の覇権主義と専制主義の体制であり、社会主義の本当の値打ちが輝くのはこれからだと大いに訴えたが、「この世界的激変が党建設、特に若い世代の中での党づくりの大きな障害になっていることは疑いない」という分析を行いました。
同時に、それから30年がたって、世界の資本主義の矛盾が、気候危機でも、貧富の格差でも、戦争の問題でも、噴き出すなかで、いま社会主義への新しい注目や期待が広がっている。それにこたえた活動が必要だ訴えました。
そして、その具体的な内容として、大会決議の第4章で、「『人間の自由』こそ社会主義・共産主義の目的であり、最大の特質」だということを、三つの角度――「利潤第一主義」からの自由、人間の自由で全面的な発展、発達した資本主義国の巨大な可能性――から解明し、人間の自由が豊かに花開く綱領の未来社会像を発展させました。この大会決定の具体化・実践として、私たちは、2回にわたる「学生オンラインゼミ」にとりくみ、「青本」と「赤本」にまとめたわけです。
党大会決定にたち戻って、いまこの内容を学び、広げることの意義をみんなのものにして、ぜひとりくんでいきたいと思います。ここにこそ、党が、歴史的後退から前進に転じていく理論的なかなめの問題がある。この内容を、みんながつかめば、必ず党建設を前進に転ずる力になり得る。そういう提案としてつかんでいただいて、この三つの課題を一体に進めていきたいと思います。
党を理論的に鍛え、すべての党員に綱領的確信とともに世界観的確信をつちかい、党の活力を増大させながら党勢拡大の飛躍をつくりだす――質と量と一体に相乗的に発展させるダイナミックな運動として「集中期間」を成功させようではありませんか。
「集中期間」をいかに成功させるかについて、三つの角度からのべました。これもヒントにしていただいて、ぜひ討論でさらに深めていただくことを願い、発言といたします。