| |TOP|目次|サイト内検索はこちら |
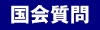 |
2006年5月27日(土)「しんぶん赤旗」
「政府の法案は最高裁判決にてらしても説明のつかないものだ」。―二十六日の衆院教育基本法特別委員会で日本共産党の志位和夫委員長は、旭川学力テスト最高裁判決(一九七六年)の内容を明らかにし、基本法一〇条を改悪する政府の根拠をくずしました。
 (写真)教育基本法改悪法案について質問する志位和夫委員長=26日、衆院教育基本法特別委 |
「教育基本法の議論では制定時の立法者の意思を踏まえた議論が重要だ」。志位氏はこう述べて、当時発行された『教育基本法の解説』を紹介しました。
この冊子の著者は文部省内の「教育法令研究会」。教育基本法制定に直接かかわった文部省調査局長の辻田力氏と東京大学教授の田中二郎氏が監修した、立法者の意思を伝える第一級の文献です。
『解説』は「政治は、政党の発生を必然的に伴い、政党間の競争と妥協によって運営されるのであるが、教育はたとえ民主主義下であっても、そのような現実的な力によって左右されないことが必要なのである」と書いています。
志位氏 この考え方はいまでも通用すると思うが、どうか。
小坂憲次文部科学相 当然だと思う。
志位氏は『解説』が「この趣旨を表すために(一〇条で)『不当な支配に服することなく…直接に…』といったのである」と書いていることを指摘し、「当然ならば、なぜ該当個所を削除するのか」と追及しました。
小坂文科相は昭和五十一年(一九七六年)の最高裁学力テスト判決に基づく改定であると、これまでの答弁を繰り返しました。
志位氏は「この最高裁判決には、私たちが肯定できない弱点も含まれているが、政府の法案はこの最高裁判決にてらしても説明のつかないものだ」として、二つの問題点を明らかにしました。
一つは「法律の定めるところにより行われる教育が、不当な支配に服するものではない」という政府の言い分についてです。
判決は「教育内容を決定する権能は誰がもつか」という問題について、「二つの極端に対立する見解」があることを指摘。その一つとして当時の政府・文部省の見解をあげました。それは現在の政府答弁とほぼ同じですが、判決はもう一つの意見と合わせて「当裁判所は、右の二つの見解はいずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできないと考える」と退けました。
志位氏が判決の内容の確認を求めたのに対し、小坂文科相は初め「この裁判そのものを全部学んでいるわけではない」と言いよどみましたが、かけよった文科省の担当者の助言を受け、「判決の中にはそのように記述されております」と認めました。
さらに判決は現行基本法の第一〇条について「教育行政機関が行う行政でも、右にいう『不当な支配』にあたる場合がありうることを否定できず」「教育行政機関が法令に基づいてする行為」であっても「『不当な支配』とならないように配慮しなければならない拘束を受けている」と述べています(別項(1))。
「間違いないですね」と詰め寄る志位氏。小坂文科相は判決の別の部分をあげて反論を試みましたが、再度追及されて「(判決には)『教育基本法一〇条一項はいわゆる法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない』と書いてあるので、その通りだ」と渋々認めました。
志位氏は「そうなると『法律に定めるところにより行われる教育が、不当な支配に服するものではない』とする政府の主張は、『最高裁判決の趣旨を踏まえ』るどころか、その結論を一八〇度ねじ曲げたものだ」と批判しました。
第二の問題は、政府が最高裁判決から「国は…、教育内容についてもこれを決定する権能を有する」という文言を引用し、基本法一〇条改定の根拠にしていることです。
しかし、判決ではこの一文に続けて「国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請される」と述べています。(別項(2))
志位氏 国家的介入が抑制的であることを、憲法の要請として明記している。政府は重く受けとめなければならない。
小坂文科相 政党政治において国家的介入が抑制的であることは否定はされない。
小坂文科相は当初、判決の関係のない部分を読み上げていましたが、志位氏の指摘で、判決が教育内容に対して国家的介入は抑制的でなければならないと示していることを認めました。
さらに判決は、基本法一〇条が「教育に対する権力的介入…に対して抑制的態度を表明したと解することはそれなりの合理性を有する」と明記し、国家的介入の抑制を保障するのは基本法一〇条だとしています。(別項(3))
志位氏 改悪法案は、現行一〇条を改変することで、最高裁判決のいう国家的介入を抑制的にする保障を取り払ってしまったのではないか。改悪案のどこに抑制を保障する条文、条項があるのか。
小坂文科相 「不当な支配に服することなく」をもって抑制的であるといえる。
志位氏 まったくの論理破たんだ。政府は、国の行為は「不当な支配」の範疇(はんちゅう)に属さないといっている。国家的介入を抑制する担保にはなり得ない。
志位氏は、この改悪法案には、教育内容への国家的介入の抑制条項が一つもないこと、すなわち国家権力が無制限・無制約に教育内容や方法に介入できる法案であること、これは教育の自由、自主性、自律性を保障した憲法に反するものだとして廃案を強く求めました。
論理的には、教育行政機関が行う行政でも、右にいう「不当な支配」にあたる場合がありうることを否定できず、問題は、教育行政機関が法令に基づいてする行為が「不当な支配」にあたる場合がありうるかということに帰着する。思うに、憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為がここにいう「不当な支配」となりえないことは明らかであるが、…教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じていることを執行する場合を除き、教基法10条1項にいう「不当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けているものと解されるのであり、その意味において、教基法10条1項は、いわゆる法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない。
国は…必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず…。政党政治の下で多数決原理によってされる国政上の意思決定は、さまざまな政治的要因によって左右されるものであるから…教育内容に対する右のごとき国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に…憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入…は、憲法26条、13条の規定上からも許されないと解することができる
教基法が前述のように戦前における教育に対する過度の国家的介入、統制に対する反省から生まれたものであることに照らせば、同法10条が教育に対する権力的介入、特に行政権力によるそれを警戒し、これに対して抑制的態度を表明したものと解することは、それなりの合理性を有する